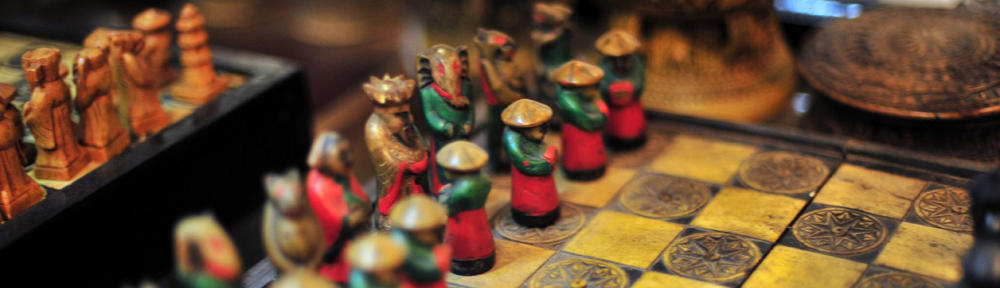雪が少ないが明け方の冷え込みは強い。間もなく2月。大荒れの日が無かったのでまだアシの穂は残り茎も立ち上がっている。湖水が茎に纏いつきながら凍り始めた。このあたりから凍結が始まる。大有珠の東面が光っている。昭和新山のドームが屋根山から黒く突き出している。静かな冬景色。
雪が少ないが明け方の冷え込みは強い。間もなく2月。大荒れの日が無かったのでまだアシの穂は残り茎も立ち上がっている。湖水が茎に纏いつきながら凍り始めた。このあたりから凍結が始まる。大有珠の東面が光っている。昭和新山のドームが屋根山から黒く突き出している。静かな冬景色。
「生活」カテゴリーアーカイブ
462 大丈夫
 先日、洞爺湖畔の使われなくなったキャンプ場で、ポリエチレンロープが巻き付いたままの樹を見つけた。丈夫なロープはいずれこの樹に食い込んでしまう。そういう痛めつけられた樹を幾度も見てきた。今日はナイフを持って出かけた。だが樹本体より先に這い登ってきていたイワガラミが痛手を受けていた。だがイワガラミも負けてはいなかった。ロープを植物体の組織に巻き込んで木部の中にしっかりと取り込んでいる。そのうえロープを二本切り離した途端、イワガラミ全体が少しずり落ちてきた。ロープを身の内にし、ロープを体の支えにしていたのだ。
先日、洞爺湖畔の使われなくなったキャンプ場で、ポリエチレンロープが巻き付いたままの樹を見つけた。丈夫なロープはいずれこの樹に食い込んでしまう。そういう痛めつけられた樹を幾度も見てきた。今日はナイフを持って出かけた。だが樹本体より先に這い登ってきていたイワガラミが痛手を受けていた。だがイワガラミも負けてはいなかった。ロープを植物体の組織に巻き込んで木部の中にしっかりと取り込んでいる。そのうえロープを二本切り離した途端、イワガラミ全体が少しずり落ちてきた。ロープを身の内にし、ロープを体の支えにしていたのだ。
利用できるものは敵味方の区別なくすべてを内的なものとし同化させ、自ら全体も適応して変化してゆく。生命はこうやって継続してきた。これこそいのちそのものの本質なのだろう。
458 コンタクトコール
 長流川にハクチョウが集まっていた。数えたら百羽くらい。体色が白く成りきっていない幼鳥もいて嘴の黄斑の形からオオハクチョウとわかる。さほど差し迫った状況にもないのだが、互いに鳴き交わし、騒々しいことこの上もない。これはコンタクトコール。群れを構成するうえでそのメンバーが自らを確認させあう重要なシステムだ。さらに群れを作って渡りをする時にはフライトコールで互いに呼び交わす。ともに長旅をする仲間や若鳥を励ましているのだろう。
長流川にハクチョウが集まっていた。数えたら百羽くらい。体色が白く成りきっていない幼鳥もいて嘴の黄斑の形からオオハクチョウとわかる。さほど差し迫った状況にもないのだが、互いに鳴き交わし、騒々しいことこの上もない。これはコンタクトコール。群れを構成するうえでそのメンバーが自らを確認させあう重要なシステムだ。さらに群れを作って渡りをする時にはフライトコールで互いに呼び交わす。ともに長旅をする仲間や若鳥を励ましているのだろう。
渡りの季節、ハクチョウのフライトコールが聞こえると家の窓を開けて空を見あげ群れを探す。低く高く飛ぶ白い列なりには、いつも荘厳さを感じる。猟犬の群れが林を駆け抜けるような気迫のこもった声を聞くと、心のどこかで、私も旅立たねばと思ってしまう。
457 茶が飲める
455 年賀状
454 北の縄文 松飾り
 しめ縄を作る機会があって、縄部分を教わって何とか作りあげた。関西からやって来て洞爺湖有珠火山マイスターとなったS氏が講師で、彼の田圃で育てあげ、湿りを入れて打ち柔らかくした稲わらを使わせてもらった。綯い方はやはり火山マイスターのBさんに教わった。飾るに際してはたと気が付き、例の伊達前浜の塩サケ(ブログ440、447)の頭を使って「箔」を付けることとし、裏庭の小さな王林を咥えさせた。松はオンコ、昆布はアルトリ岬産。これぞ地のものを使った北の縄文、ジオパーク松飾り。
しめ縄を作る機会があって、縄部分を教わって何とか作りあげた。関西からやって来て洞爺湖有珠火山マイスターとなったS氏が講師で、彼の田圃で育てあげ、湿りを入れて打ち柔らかくした稲わらを使わせてもらった。綯い方はやはり火山マイスターのBさんに教わった。飾るに際してはたと気が付き、例の伊達前浜の塩サケ(ブログ440、447)の頭を使って「箔」を付けることとし、裏庭の小さな王林を咥えさせた。松はオンコ、昆布はアルトリ岬産。これぞ地のものを使った北の縄文、ジオパーク松飾り。
松を飾るのは遠く雲南、照葉樹林文化からの伝えだというが、数千年をえて弥生式文化のこちら、ナラ落葉樹林文化の地の果ての仁左衛門宅が落ち着く先となりました。北の縄文人、オホーツク文化人たちは鮭と深~い縁で繋がっておりました。鮭は北の民が冬を越す「命の依代」でした。
453 ハシジロガラス
451 旨いぞホタテ
 友人からホタテが届いた。大ぶりの殻つきのが15個、「生きがいいぞ」と油断をしたら指を噛みつかれた。いつもなら正月用に殻ごと熱湯に入れ、瞬時に取り出して貝柱を保存に回すのだが、今日はその前祝、極上の北海の絶品をそのまま味わった。まずは刺身。貝柱は厚めの3枚にそぎ切り、ヒモはぶつ切り、エラはそのまま。産卵期を終え、卵巣は小さいが短冊に。貝柱の固く締まって甘いことよ。卵巣は新鮮なウニの味。潤沢な磯の香のヒモは何とも言えない歯触りで、懐かしい赤貝を思い出す。ワサビは野暮だよ、要らないね。 あと一品、膨らんでいる白い下側の殻にむき身とバターと醤油を入れ火にかける。アツアツのところをウロごと二口ぐらいで頬張る。
友人からホタテが届いた。大ぶりの殻つきのが15個、「生きがいいぞ」と油断をしたら指を噛みつかれた。いつもなら正月用に殻ごと熱湯に入れ、瞬時に取り出して貝柱を保存に回すのだが、今日はその前祝、極上の北海の絶品をそのまま味わった。まずは刺身。貝柱は厚めの3枚にそぎ切り、ヒモはぶつ切り、エラはそのまま。産卵期を終え、卵巣は小さいが短冊に。貝柱の固く締まって甘いことよ。卵巣は新鮮なウニの味。潤沢な磯の香のヒモは何とも言えない歯触りで、懐かしい赤貝を思い出す。ワサビは野暮だよ、要らないね。 あと一品、膨らんでいる白い下側の殻にむき身とバターと醤油を入れ火にかける。アツアツのところをウロごと二口ぐらいで頬張る。
449 食足りて礼節
 国道37号線の橋から見下ろす長流川の河口近くの河原には水鳥が集まっている。オオハクチョウ、カルガモ、オオセグロカモメ、ミヤコドリもいるようだ。浅瀬や岸辺には遡上し終えて死んだ鮭がたくさん見える。カモメは腹いっぱいに違いない。カラスたちも喰い飽きて編成し終えた群れでどこかの畑に集まっているのだろうか。ホッチャレ鮭目当てで毎年飛来して春まで留まるオジロワシ、オオワシもすでに姿を見たという話を聞いてはいるが、ここにはいないようだ。
国道37号線の橋から見下ろす長流川の河口近くの河原には水鳥が集まっている。オオハクチョウ、カルガモ、オオセグロカモメ、ミヤコドリもいるようだ。浅瀬や岸辺には遡上し終えて死んだ鮭がたくさん見える。カモメは腹いっぱいに違いない。カラスたちも喰い飽きて編成し終えた群れでどこかの畑に集まっているのだろうか。ホッチャレ鮭目当てで毎年飛来して春まで留まるオジロワシ、オオワシもすでに姿を見たという話を聞いてはいるが、ここにはいないようだ。
小春日和、集まっている鳥たちは何かのんびりしている。オジロワシ、オオワシがいてもキタキツネがうろうろしていても満ち足りているとこんな具合だ。 中国漢代に「倉廩(そうりん=穀物庫)満ちて礼節を知る」という言葉があるそうだ。納得できる風景だ。