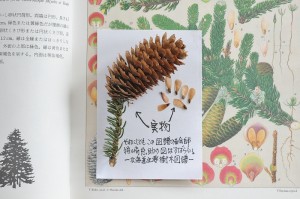 ドイツトウヒの球果(マツカサ)が机の上で乾燥し苞鱗が開き、翼をもった薄い種子がこぼれ落ちていた。椅子の上に立ち種子を放すとよく回りながらゆっくりと落下する。私たちは気がつかないが、種子は私たちの頭上を飛んでいる。クルクル回りながら、吹き上げる乾いた風に乗って谷を越え尾根を越えて飛び続けている。着地した場所が良ければ幸運、不運なものは地に還る。
ドイツトウヒの球果(マツカサ)が机の上で乾燥し苞鱗が開き、翼をもった薄い種子がこぼれ落ちていた。椅子の上に立ち種子を放すとよく回りながらゆっくりと落下する。私たちは気がつかないが、種子は私たちの頭上を飛んでいる。クルクル回りながら、吹き上げる乾いた風に乗って谷を越え尾根を越えて飛び続けている。着地した場所が良ければ幸運、不運なものは地に還る。
55 レモンとクルミ
 湘南の陽射しと海風を受けて育ったレモンとオレンジが知人から届いた。濃い照葉の中に黄金色が輝く果樹園の光景を思いながら、はて、どうやっていただこうと考えた。思い立ったのが旬のオーガニックレモンを使ったレモンピールだ。皮ごと苦さを味わえる。それと私の住む壮瞥町に開拓の時代から受け継がれている美味しいクルミ。これをコラボさせて強い味のドライジャムに仕立てよう。コンセプトは「大地の息吹」だ。
湘南の陽射しと海風を受けて育ったレモンとオレンジが知人から届いた。濃い照葉の中に黄金色が輝く果樹園の光景を思いながら、はて、どうやっていただこうと考えた。思い立ったのが旬のオーガニックレモンを使ったレモンピールだ。皮ごと苦さを味わえる。それと私の住む壮瞥町に開拓の時代から受け継がれている美味しいクルミ。これをコラボさせて強い味のドライジャムに仕立てよう。コンセプトは「大地の息吹」だ。
 レモンとクルミ、しっかり者同士をくっつけるにはスパイスも必要。シナモン、ジンジャーはよく使うので、今回は敬愛するシュウォーツ爺さんのレシピを参考にコリアンダーを使ってみる。出来た味は苦く酸っぱく甘く、ローストしたクルミの香りが鼻に抜ける。ミンスミートのようなガツンとくる味だ。エスニックかつマイルドなのは仕事人コリアンダーの業。クラッカーにたっぷり載せてもよいし、春野菜のサンドイッチはどうだ。生地に混ぜ込んでビスケットやリーンなパンもいい。春だね、何かを作りたくなる。
レモンとクルミ、しっかり者同士をくっつけるにはスパイスも必要。シナモン、ジンジャーはよく使うので、今回は敬愛するシュウォーツ爺さんのレシピを参考にコリアンダーを使ってみる。出来た味は苦く酸っぱく甘く、ローストしたクルミの香りが鼻に抜ける。ミンスミートのようなガツンとくる味だ。エスニックかつマイルドなのは仕事人コリアンダーの業。クラッカーにたっぷり載せてもよいし、春野菜のサンドイッチはどうだ。生地に混ぜ込んでビスケットやリーンなパンもいい。春だね、何かを作りたくなる。
54 春の声
53 瞬膜
52 斑雪
51 春の兆し
50 大仮宿(おおかりやど)
 3,11東日本大震災から一年経った。全国の死者・行方不明者は1万9510人にのぼるという。私は昔から海が好きだったからとても心が痛む。被害の大きかった釜石の近くに、大仮宿という小さな入り江と砂浜がある。気がかりでグーグルアースで見たら津波が奥へ280mも駆け上がった痕跡があった。地形図に合わせると到達地点の高さは海面から30mほどだ。緑の草地は消え、一つ建物の基礎部分だけが残っている。
3,11東日本大震災から一年経った。全国の死者・行方不明者は1万9510人にのぼるという。私は昔から海が好きだったからとても心が痛む。被害の大きかった釜石の近くに、大仮宿という小さな入り江と砂浜がある。気がかりでグーグルアースで見たら津波が奥へ280mも駆け上がった痕跡があった。地形図に合わせると到達地点の高さは海面から30mほどだ。緑の草地は消え、一つ建物の基礎部分だけが残っている。
 26年前、ここの海岸でカサガイの調査をした。手元に百数十個の標本が残っている。オオカリヤド Lamminaria zone=コンブ帯。今は属名が変わっているが北太平洋種のCollisella emydia ベッコウシロガイと暖かい海からの Notoacmea gloriosa サクラアオガイ、よく似た種が同時に見つかった。北と南の生きものたちの接点三陸の海。その時この浜の番屋でとても甘いコーヒーと暖かい食事をたっぷり御馳走になった。冷えきった身体に好意が嬉しかった。お世話になった人はそこにはすでにいないとしても、今回の津波で番屋にいた人たちは無事だったのだろうか。この浜では明治26年(1896年)、明治三陸大津波で84名が命を失っている。 津波から一年過ぎて、海中の生きものたちは復活し、元の自然に戻ったであろう。でも何時か、きっとまた大津波はここにやってくる。 たまたま私がかかわった、間口100mほどの小さな浜での出来事だが、私たちはあたりまえの自然の中で、その自然をどう生きればよいのかを、あらためて問われている。
26年前、ここの海岸でカサガイの調査をした。手元に百数十個の標本が残っている。オオカリヤド Lamminaria zone=コンブ帯。今は属名が変わっているが北太平洋種のCollisella emydia ベッコウシロガイと暖かい海からの Notoacmea gloriosa サクラアオガイ、よく似た種が同時に見つかった。北と南の生きものたちの接点三陸の海。その時この浜の番屋でとても甘いコーヒーと暖かい食事をたっぷり御馳走になった。冷えきった身体に好意が嬉しかった。お世話になった人はそこにはすでにいないとしても、今回の津波で番屋にいた人たちは無事だったのだろうか。この浜では明治26年(1896年)、明治三陸大津波で84名が命を失っている。 津波から一年過ぎて、海中の生きものたちは復活し、元の自然に戻ったであろう。でも何時か、きっとまた大津波はここにやってくる。 たまたま私がかかわった、間口100mほどの小さな浜での出来事だが、私たちはあたりまえの自然の中で、その自然をどう生きればよいのかを、あらためて問われている。
49 ニシン漬
48 手前味噌
その国の市場や路地裏にはその国の匂いがある。一本裏通りの定食屋や屋台には、等しく日常の味と匂いがあふれ、賑わう音に混じって庶民の食う音、啜る音がきこえてくる。日本で言うなれば、それは味噌と醤油の味と匂いが横丁の香りだ。はるかな昔から、草醤(くさびしお)・魚醤(うおびしお)の国なのだ。 そこで思い立って、久しぶりに味噌作りに取りかかる。地方には伝統的なたくさんの味噌の製法がある。味、香りが中庸で、少し塩を押さえた甘口の江戸味噌を仕込むことにした。好みにもよるが、作って2年、3年目になると色が濃くなり味も深みも増して、私は3年位がいちばん旨いと思う。暖かくなり夏に向かって熟成が進んでゆき、味噌らしくなってゆく。北海道の三月はまだ寒仕込みのシーズンです。どうですこの地方はマメの国、地元の豆で自家製の味噌を作ってみませんか。
 マメは壮瞥町のつるの子大豆。味の良い豆はそのまま旨い味噌となる。麹は道産米「ほしのゆめ」の米麹が手に入った。塩は20年来の格安で旨いシャークベイの天日塩。基本となるレシピなので配合は単純にして、好みに応じての手直しも簡単だ。一昼夜浸して、膨潤させたマメをとろ火で5時間煮る。その間に、麹と塩を混ぜて塩切り麹を作る。味噌の旨さは大豆で決まるという。煮あがった豆は納得のいく美味しい豆だった。
マメは壮瞥町のつるの子大豆。味の良い豆はそのまま旨い味噌となる。麹は道産米「ほしのゆめ」の米麹が手に入った。塩は20年来の格安で旨いシャークベイの天日塩。基本となるレシピなので配合は単純にして、好みに応じての手直しも簡単だ。一昼夜浸して、膨潤させたマメをとろ火で5時間煮る。その間に、麹と塩を混ぜて塩切り麹を作る。味噌の旨さは大豆で決まるという。煮あがった豆は納得のいく美味しい豆だった。
 マメを挽く。要するに均一につぶれていればよいわけで、いろいろな方法が用いられてる。擂る、搗く、叩く、踏みつける。私は簡単な家庭用のモーター付きのを使っている。14kgほどの豆を挽くのに30分で作業を終えた。これを塩切り麹と良く混ぜる。煮汁を使いハンバーグを捏ねる軟らかさに調整する。今回は2リットル使った。一度に全量を混ぜられないので、4回分に分けそれぞれ完璧によく混ぜた後まとめることにしている。
マメを挽く。要するに均一につぶれていればよいわけで、いろいろな方法が用いられてる。擂る、搗く、叩く、踏みつける。私は簡単な家庭用のモーター付きのを使っている。14kgほどの豆を挽くのに30分で作業を終えた。これを塩切り麹と良く混ぜる。煮汁を使いハンバーグを捏ねる軟らかさに調整する。今回は2リットル使った。一度に全量を混ぜられないので、4回分に分けそれぞれ完璧によく混ぜた後まとめることにしている。
 均一になった材料を丸め、味噌甕の中に打ちつけるようにして空気を追い出しながら詰め込む。すき間があるとカビが生えやすいからだ。つめた表面にカビがつくので、さらしや丈夫な紙蓋をし、ヘリの部分を市販の味噌で封をする。これは近所の人から習った裏技だ。あとは重石を乗せ熟成を待つだけ。私は1年以上待つことにしている。香り立つその味はまことに手前味噌だが、芳醇濃厚にして他者を盛り立てる凄腕の名脇役だ。
均一になった材料を丸め、味噌甕の中に打ちつけるようにして空気を追い出しながら詰め込む。すき間があるとカビが生えやすいからだ。つめた表面にカビがつくので、さらしや丈夫な紙蓋をし、ヘリの部分を市販の味噌で封をする。これは近所の人から習った裏技だ。あとは重石を乗せ熟成を待つだけ。私は1年以上待つことにしている。香り立つその味はまことに手前味噌だが、芳醇濃厚にして他者を盛り立てる凄腕の名脇役だ。






