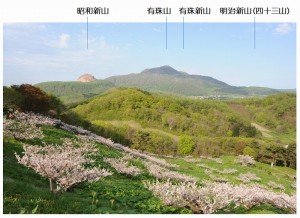「ひとやねて、くやしやきみのふたこころ、うらみてはなく、うらみてはなく」こんな判じ文を思い出した。昨日はまだ小指の先ほどの、名前知らずのヒトヨタケ。朝の雨をほつれた傘に乗せ、今日はもう、自らの酵素で身の内から溶けはじめてこの体たらく。一夜で溶けてゆく覚束なさは、哀れなのか見事なのか。恨みをつぶやく暇もない。でも闇に紛れて襞という襞から胞子を落とし、次の世代はいま、どこか土臭い世界で眠りについている。
「ひとやねて、くやしやきみのふたこころ、うらみてはなく、うらみてはなく」こんな判じ文を思い出した。昨日はまだ小指の先ほどの、名前知らずのヒトヨタケ。朝の雨をほつれた傘に乗せ、今日はもう、自らの酵素で身の内から溶けはじめてこの体たらく。一夜で溶けてゆく覚束なさは、哀れなのか見事なのか。恨みをつぶやく暇もない。でも闇に紛れて襞という襞から胞子を落とし、次の世代はいま、どこか土臭い世界で眠りについている。
95 大有珠の岩塔
94 金銀珊瑚の
93 クモの子を散らすように
92 思い出のアンニンゴ
91 幕の下りないエピローグ
90 おなじみさん
 周囲43kmの洞爺湖湖畔には58基の野外彫刻が点在している。「とうや湖ぐるっと彫刻公園」だ。野にあって初めて生命を得る造形群。緑の風の中、湖面や島影と重なる作品はいずれも「生きている」ことを謳い、豊かな自然を讃えているようだ。生活感あふれる裸婦像は近隣に住む人たちとも馴染んで、顔見知りの知人のような存在だ。そのほか、湖を渡る風に遊ぶ少女も居れば、独り湖を眺める少年の像もある。荒ぶるオテナの風貌にも似た彫像もある。蒼空を映す鏡面の造形も、大地の移ろいを感じさせる石彫や石組みもある。いずれも力量あふれた作家たちの手によるものだ。フルマラソンの距離ぴったりのなだらかな湖畔、サクラの花と新緑の下を彫刻をめぐりながら心地よい汗をかくのも「洞爺湖有珠山ジオパーク」の楽しみ方。自転車ならばゆっくり半日コース。
周囲43kmの洞爺湖湖畔には58基の野外彫刻が点在している。「とうや湖ぐるっと彫刻公園」だ。野にあって初めて生命を得る造形群。緑の風の中、湖面や島影と重なる作品はいずれも「生きている」ことを謳い、豊かな自然を讃えているようだ。生活感あふれる裸婦像は近隣に住む人たちとも馴染んで、顔見知りの知人のような存在だ。そのほか、湖を渡る風に遊ぶ少女も居れば、独り湖を眺める少年の像もある。荒ぶるオテナの風貌にも似た彫像もある。蒼空を映す鏡面の造形も、大地の移ろいを感じさせる石彫や石組みもある。いずれも力量あふれた作家たちの手によるものだ。フルマラソンの距離ぴったりのなだらかな湖畔、サクラの花と新緑の下を彫刻をめぐりながら心地よい汗をかくのも「洞爺湖有珠山ジオパーク」の楽しみ方。自転車ならばゆっくり半日コース。