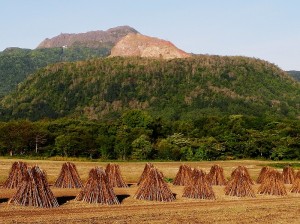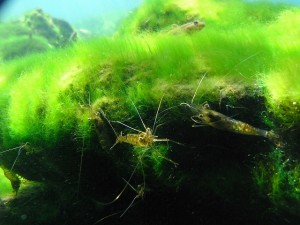チョウセンゴミシは日本薬局方にも載っている古くから知られた生薬だ。五味子とは含まれる甘味・酸味・辛味・塩(鹹)味・苦味に由来すると言う。秋の日の午後、長流川の上流で以前に見つけておいた株を友人を伴って見に行った。数年前から「ぜひ案内しよう」と約束していた場所だ。瀬音のする山合いに夕闇の迫る頃、ほのかに赤く色付いた幾つかの房に再会。ウスリーの作家、バイコフを教えてくれた旧友との約束がこれで果たせたというものだ。
チョウセンゴミシは日本薬局方にも載っている古くから知られた生薬だ。五味子とは含まれる甘味・酸味・辛味・塩(鹹)味・苦味に由来すると言う。秋の日の午後、長流川の上流で以前に見つけておいた株を友人を伴って見に行った。数年前から「ぜひ案内しよう」と約束していた場所だ。瀬音のする山合いに夕闇の迫る頃、ほのかに赤く色付いた幾つかの房に再会。ウスリーの作家、バイコフを教えてくれた旧友との約束がこれで果たせたというものだ。
仁左衛門の不思議な世界
気紛れ仁左衛門の行雲流水・森羅万象がここにあります お立ち寄りください